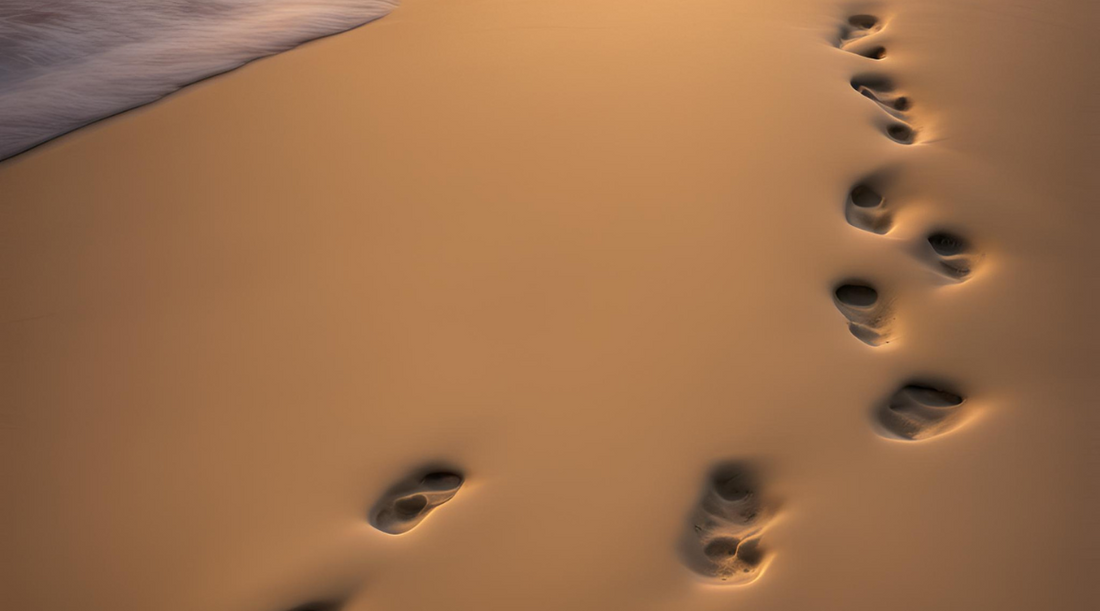
『火垂るの墓』と『かぐや姫の物語』: 高畑勲が描いた命の儚さ
共有する
高畑勲が描く「命の儚さ」とは?

アニメーションは、夢や冒険を描くものと思われがちですが、高畑勲監督の作品は、人生の儚さや人間の運命に寄り添うような深いテーマを持っています。
特に『火垂るの墓』(1988年)と『かぐや姫の物語』(2013年)は、彼の哲学が色濃く表れた作品です。『火垂るの墓』では戦争によって命を奪われる現実の悲しみを、『かぐや姫の物語』では人生の喜びと別れの切なさを描いています。
この2作品に共通するのは、「避けられない運命の中で、どのように生きるか」という問いかけです。本記事では、これらの作品を通して、高畑勲監督が私たちに伝えたかったメッセージを探ります。
1. 『火垂るの墓』: 戦争と喪失のリアルな描写

『火垂るの墓』は、戦争孤児となった兄妹・清太と節子が、生き抜こうとする姿を描いた作品です。戦争をテーマにしたアニメは数多くありますが、本作が特別なのは、戦争の「英雄的な部分」を一切排除し、個人の視点から「生きることの厳しさ」を描いている点です。
物語の中で印象的なのは、火垂る(ホタル)の存在です。夜空に美しく舞うホタルは、命の儚さを象徴しており、束の間の輝きを放ちながらも、すぐに消えてしまいます。清太と節子の運命も、まるでホタルのように、希望を持ちながらも消えゆくものとして描かれます。
本作が観る者の心に深く響くのは、そのリアリズムにあります。戦争映画でありながら、悲劇を誇張せず、むしろ淡々とした日常の積み重ねを描くことで、より一層の現実味を持たせています。その結果、観客は清太と節子に対してただ同情するのではなく、「自分ならどうするか?」と考えさせられるのです。
2. 『かぐや姫の物語』: 美しくも切ない人生の軌跡

一方、『かぐや姫の物語』は、日本最古の物語「竹取物語」をアニメーション化した作品ですが、単なる昔話の再現ではなく、「生きることの喜びと悲しみ」をテーマにした壮大な人間ドラマとなっています。
かぐや姫は月の世界から地球へとやってきますが、最終的には元の世界へ戻らなければならない運命にあります。彼女は地上での生活を愛し、人間としての感情や喜びを知るのですが、それでも避けられない別れが待っています。この構造は、『火垂るの墓』の兄妹が戦争によって命を奪われるのと同じく、「どうすることもできない運命」に翻弄される人間の姿を映し出しています。
また、本作のアニメーション表現も特筆すべき点です。まるで日本画が動いているかのようなタッチで描かれた映像は、かぐや姫の儚さを際立たせ、物語の美しさを一層引き立てています。特に、彼女が感情を爆発させるシーンでは、筆のタッチが荒々しくなり、その心の揺れが視覚的に伝わってきます。
3. 2つの作品に共通する「命の儚さ」

『火垂るの墓』と『かぐや姫の物語』は、一見すると全く異なる時代背景とストーリーを持つ作品ですが、共通して「命の儚さ」というテーマが貫かれています。
どちらの作品も、「大切なものは永遠ではない」という現実を突きつけます。清太と節子は、戦争という避けられない状況の中で命を落とし、かぐや姫は、生きることの喜びを知りながらも、元の世界へ帰る運命を受け入れなければなりません。
しかし、どちらの作品にも「悲しいだけではない美しさ」があります。『火垂るの墓』では、清太が節子を愛し、懸命に生きようとする姿が描かれ、『かぐや姫の物語』では、彼女が人間としての感情を持ち、「生きる」ことそのものを楽しむ瞬間があるのです。
まとめ: 高畑勲が私たちに伝えたかったこと
高畑勲監督は、これらの作品を通して、「人生は儚いからこそ、美しい」というメッセージを私たちに届けました。どんなに努力しても避けられない別れや、理不尽な運命は存在します。しかし、それでもなお、人は愛し合い、喜びを見つけ、輝く瞬間を生きていくのです。
『火垂るの墓』を観た後、家族や友人の大切さを改めて感じ、『かぐや姫の物語』を観た後、この世界の美しさに目を向けたくなる――そんな感覚を抱く方も多いでしょう。
もしまだこの2作品を観たことがない方がいれば、ぜひ一度触れてみてください。きっと、高畑勲監督が遺した「人生の美しさ」を感じることができるはずです。



