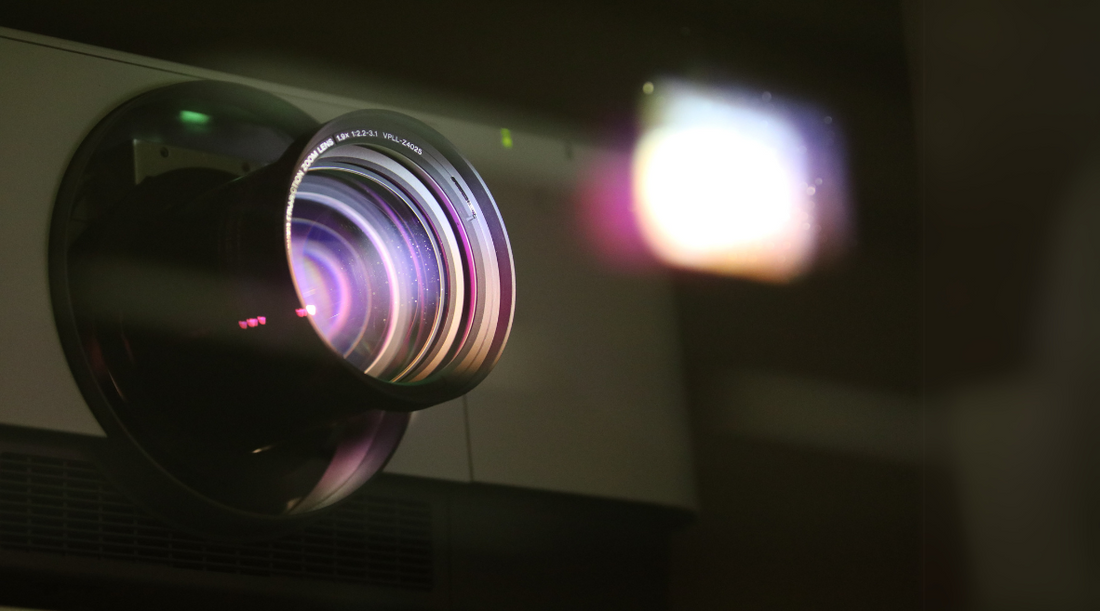
映画監督 石井岳龍の軌跡 - 自主映画からの出発と商業デビュー
共有する
石井岳龍の映画監督としての軌跡 - 自主映画からの出発と商業デビュー
異端の映画作家の誕生 - 自主映画からの出発
石井岳龍(いしい がくりゅう、旧名:石井聰亙)は1957年に福岡で生まれ、大学入学直後の1976年に自主映画グループ「狂映舎」を設立したことから彼の映画人生が始まった。彼が8mmで撮った自主制作映画『高校大パニック』(1976年)は学園叛乱を描いた処女作であり、学生映画ながらもプロデューサーの目に留まった。この作品は1978年に日活によって劇場用映画としてリメイクされ、この時点で石井はインディーズ映画の世界に頭角を現した。
石井の大学在学中の卒業制作として製作した16mm長編『狂い咲きサンダーロード』(1980年)は彼の才能を決定的なものにした。若者暴走族の抗争を描いたこの野心作は、当時学生だった石井自身の手で制作されたにもかかわらず、内容の過激さとエネルギーが評価され、東映系で35mmフィルムにブローアップされ全国劇場公開された。この作品は日本映画史上「幻の名作」とも呼ばれ、長らく西側では見ることが難しかったが、近年リマスター版が海外でも発売され再評価が進んでいる。
石井は「映画学校で教わる方法ではなく、パンクミュージシャンが楽器を我流で操るように、自分独自のやり方で映画を撮った」と言われており、その無鉄砲な作風は後に日本サイバーパンク映画の源流となった。海外の評論家からも「黒澤明以来の新しい才能」と絶賛され、日本のみならず世界のカルト映画ファンに衝撃を与えた作品となった。
商業デビューと80年代カウンターカルチャーの象徴

1982年、石井は自主制作活動の集大成ともいえる作品『爆裂都市 BURST CITY』で本格的に商業監督デビューを果たした。この作品は近未来の廃墟都市を舞台にパンクロッカーたちの抗争を描いたもので、荒削りながらも凄まじいエネルギーとパンク音楽の融合、そして無法者たちの退廃的な未来像が特徴となり、「日本映画界における80年代カウンターカルチャーの金字塔」と称されるカルト作品となった。
早稲田大学出身の映画監督たち(森田芳光や長崎俊一など)と共にぴあフィルムフェスティバル(PFF)で名前を連ねた石井は、その異端的な映像センスによって1980年代の日本映画に突然現れた革命児とみなされるようになる。同年、名匠長谷川和彦に誘われ若手監督集団ディレクターズ・カンパニーの設立にも参加し、日本映画界で独自の立ち位置を確立していった。
続く『逆噴射家族』(1984年)は石井にとって初の商業ベースでの単独監督作となり、平凡な日本の家庭が徐々に狂気に蝕まれていくブラックコメディとなった。石井はこの作品で家族の狂乱を風刺的かつシュールに描き、ベルリン国際映画祭フォーラム部門で注目されるなど海外からも評価を受けた。実際、本作はイタリアの第8回サルソ映画祭でグランプリに輝き、国内外で高い評価を獲得している。
映像と音楽の革新的融合

石井の最大の特徴のひとつとして、映像と音楽の革新的な融合がある。特に『爆裂都市』では単なるBGMではなく、音楽自体が映像のリズムと物語構造を形成する重要な要素となっている。ザ・ロッカーズやザ・スターリンといった実在のパンクロックバンドの演奏シーンを物語に組み込み、ストーリーのクライマックスをライブさながらの熱狂で描き出した。
こうしたロック音楽と映画の直接的な融合は当時の日本映画では前例が少なく、石井は音の衝撃と映像の暴力性をシンクロさせる独自のスタイルを築いた。実際、彼の初期作品には福岡のパンクバンド(ザ・Mods、ザ・Roostersなど)のメンバーが多数出演し、劇中でバンド「バトルロッカーズ」としてライヴシーンを繰り広げている。
ノイズミュージックやハードコア・パンクの轟音に乗せて映像がカットアップ的に畳みかける演出は、観客に音響体験と視覚体験の融合した強烈な刺激を与え、「映画による暴動」と評されるようなカルト的熱狂を生んだ。石井自身も、ボーカルとして「石井聰亙&バチラス・アーミー・プロジェクト」というバンドで音楽活動を行い、自身の映画『アジアの逆襲』(1983年)の音楽を担当して同名のアルバムを発表するなど、音と映像の両面で才能を発揮していた。
停滞期からの復活と表現の進化

『逆噴射家族』以後、石井はしばらく長編映画を撮れない時期が続いた。1980年代後半から90年代初頭にかけて、『GOD STONE』や『箱男』の映画化企画など幾つかの試みが未完に終わり、アメリカでの撮影企画も実現しなかった。しかしこの期間中、石井は日本のジャパニーズ・パンク/ニューウェーブ音楽シーンと共闘し、数多くのミュージックビデオや実験的短編映画の制作に打ち込んだ。
1990年代に入り、石井は約10年ぶりの劇場用長編となるサイコサスペンス映画『エンジェル・ダスト』(1994年)でカムバックを果たす。同作は猟奇殺人事件を題材にしつつ映像的実験性を打ち出し、バーミンガム映画祭グランプリ受賞など国際的にも評価された。以後も神秘主義的な青春ファンタジー『水の中の八月』(1995年)やノスタルジックなモノクロ幻想譚『ユメノ銀河』(1997年)などを発表し、オスロ映画祭グランプリ受賞など着実に評価を高めた。
2000年には時代劇と特殊効果を融合させた超大作『五条霊戦記 GOJOE』を監督し、大手配給(東宝)で全国公開された。さらに21世紀に入ると、石井は55分という短めの上映時間ながら電気と暴力が炸裂する伝説的カルト映画『ELECTRIC DRAGON 80000V』(2001年)を発表。これは俳優の浅野忠信と永瀬正敏を迎えたモノクロームの怪作で、アヴァンギャルドなノイズ音楽、猛烈な高速編集、モノクロ映像による55分間の猛襲は石井自身のパンク的ルーツを凝縮した爆発的クリエイティビティの発露となり、過去の作品すら凌駕する勢いで観る者を圧倒した。
こうした90年代以降の作品群は、それまでの「暴走族パンク映画」のイメージを塗り替え、石井の映像作家としての新たな地平を示すものとなった。彼は常に映像表現の革新に挑み続け、日本映画界における異端の映像作家としての地位を確立していった。



